── 西木めいさんインタビュー
あなたは、わが子の学校生活のことで「先生に何をどう伝えたらいいんだろう…」と悩んでいませんか?
確かに、発達のグレーゾーンの子どもの困りごとは、一見わかりにくく、先生にもうまく伝わらないことが多いですよね。
結果、「先生にわかってもらえない…」「結局家だけで頑張るしかない…」と感じている方も少なくありません。
でも実は、ちょっとした伝え方のコツと準備をするだけで、先生との連携がスムーズになり、子どもが安心して学校生活を送れるようになるんです。
そこで今回は、学校カウンセラーとして先生と親の“橋渡し役”を務めるめいさんに、グレーゾーンの子の困りごとを上手に伝える方法を伺いました。
学校とのやり取りに悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
■ 先生と親が、同じ未来を見て進むために
めいさんは小学校・中学校でスクールカウンセラーを務め、子ども・保護者・先生の橋渡し役をしています。
「今できることを親子と一緒に考え、スモールステップで解決する“作戦会議”の要素が強いカウンセリングをしています」と語ります。
もともと小学校や特別支援学校の教員として15年間、さまざまな子どもたちと向き合ってきためいさん。
現場では、保護者対応のストレスで心を病み、教職を辞めていく優秀な先生たちを何人も見送ってきました。実際に、自身の夫も教員として同じ壁にぶつかり、3年間の療養休暇を経て退職した経験があります。
「先生と親が、子どもを中心に同じ方向を向けたら、学校はもっと安心できる場所になるはず」
そう確信しためいさんは、教室の外から、先生と親が“寄り添い合えるよう双方の橋渡しをしたい”と、スクールカウンセラーとしての道を選んだのです。

■ “見えにくい困りごと”を抱える子どもたち
グレーゾーンと呼ばれる子は一見“普通”に見える。でも、集団の中ではうまくいかない。
得意なことと苦手なことが混ざっているからこそ、周囲には理解されにくく、「あの子、わがまま」「やればできるのに」と誤解されやすいのです。
めいさんは言います。
「困りごとは、子どもからのSOSなんです。わざと困らせたいわけじゃない。そうしなければ、自分を保てないくらい子どもは今追い詰められている、必死に出しているサインなんです。」
■ 親として何ができる?
「子どもの困り行動は、叱るべき『問題』ではなく、SOSのサインです。」
めいさんはそう保護者に伝えます。まずは、そのSOSを親自身が見逃さずに捉え続けることが、何よりの支援の始まりです。
では、そのSOSをどう学校と共有すればいいのでしょうか?
「親は家庭での専門家、先生は学校での専門家。それぞれの立場を大事にして、無理に全部の支援を丸ごと渡す必要はありません。」
幼稚園でうまくいった支援を小学校にそのままパッケージで渡すよりも、「先生から現場を見てのアドバイスをいただきたい」という協力の姿勢で話すほうが、先生の試行錯誤を引き出し、より良い形に育っていくのです。

■ 伝える前に整理しておきたいこと
先生に相談する前に、考えておきたいポイントを教えてもらいました。
・具体的な困りごとの場面をまとめる(いつ、どこで、どんなとき)
・家庭でうまくいった支援エピソード、うまくいかなかったエピソード
・親としての一年後の願いと、十年後の願い
・子どもの好きなこと・得意なことを30個挙げる
・医療機関や療育機関からのアドバイス
「保護者から具体的なエピソードを教えてもらえると、先生も『家庭でこううまくいったなら、学校ではこんな形で応用できそうだな』と、自分なりに工夫や試行錯誤がしやすくなるんです。」
ゴールを共有しそこから逆算すると、先生も親も今すべきことがイメージしやすくなるんです。
■ 周りの子を育てるという視点
困っている子にばかり目を向けがちですが、めいさんは「周りの子を育てる」大切さも伝えています。
「例えば暴言を吐いてしまう子がいたとき、周りの子が『まただ!迷惑!』と思うか、『あ、今あの子は辛いんだな』と思えるかで、グレーゾーンの子の困りごとは格段に減ります。」
「だから、先生と一緒に『周りの子をどう育てるか』を考えることも、グレーゾーンの子の居場所を守る一つの方法なんです。」

■ 「様子を見ましょう」「みんなと同じ」の落とし穴
一方で、うまくいかない例として多いのが「様子を見ましょう」という言葉。
めいさんは「曖昧な様子見」はNGとし、具体的に記録して、次の面談で比較する仕組みを提案しています。
また『みんなと同じようにしなさい』もNG。
「子どもにとって意味がわからず苦痛なだけ。大事なのは『なぜそうするのか』『自分にどんなメリットがあるのか』を伝えてあげることです。」
■ 親ができる“小さな大切な一歩”
「サポートブックを作ってその内容を先生と共有するところからスタートしてみるのはいいと思います。でも大切なのは、形だけの行動ではなく「先生に相談していいんだ」という気持ちを持つことです。」
「先生は忙しいし、迷惑かも…」と思いがちですが、実は学校では情報が不足していて、先生が困っていることも多いそう。
だからこそ、サポートブックや連絡帳など、どんな形でもいいので、家庭でのエピソードや子どもの様子を先生に伝えることがとても大切です。
そして困りごとの打開策は、誰かと繋がって試行錯誤を辞めないことが大切だとめいさんは伝えています。
「困りごとは一人で抱えない。必ず他の大人とつながってください。子どもを中心とした“応援団ネットワーク”を作れば、解決できることは無限にあります。」
■ めいさんからのメッセージ
「グレーゾーンの子を育てるのは、本当にエネルギーが要ります。でも、その経験は親御さんの人生の“経験値爆上げ”の時間でもあります。」
「目の前の小さな一歩が、必ず18歳の未来につながります。『できることは無限にある』。だから、大丈夫。一緒に試行錯誤していきましょう!」
■さいごに
今回は、学校や先生に“見えにくい困りごと”をうまく伝えるためのポイントを、スクールカウンセラーのめいさんに伺いました。
「先生は現場の専門家、親は家庭の専門家」。役割を分けて協力することで、子どもを中心とした安心できる学校生活が整っていきます。
家庭での小さな気づきやエピソードを、遠慮せず学校に届けてみてはいかがでしょうか?
親と先生が同じ方向を向いて支え合えば、きっと子どもの笑顔はもっと増えていきますよ。
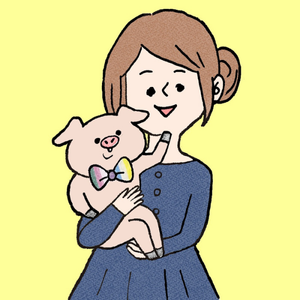
西木めいさん
スクールカウンセラー/発達凸凹支援コンサルタント
教員経験を経て、親と先生が同じ未来を見て進む仕組みを広める専門家。2,500件以上の相談を解決。
SNSやオンライン講座で情報発信中。
著書に『発達障害のある子を支える 担任と保護者の連携ガイド』を執筆。
Instagram:@mei_gakko
「子どもの自立を叶える!親子が勇気にあふれる凸凹子育てメール講座」はこちらから
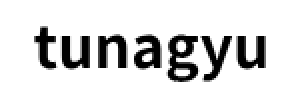

 (5).png) 閲覧数: 297
閲覧数: 297
 閲覧数: 259
閲覧数: 259
 閲覧数: 257
閲覧数: 257
 (12).png) 閲覧数: 257
閲覧数: 257
 閲覧数: 247
閲覧数: 247
 閲覧数: 231
閲覧数: 231
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 228
閲覧数: 228
 閲覧数: 205
閲覧数: 205